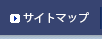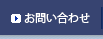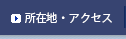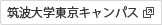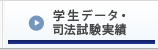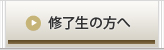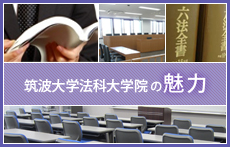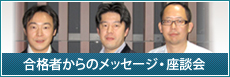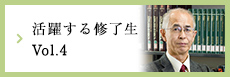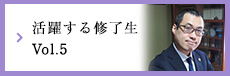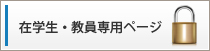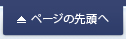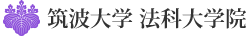| 1 合格者のプロフィール | |
| K.K. | さん:法学部出身。学部時代に旧司法試験受験歴あり。35年間、銀行・損害保険会社でリスク管理、融資、社債・株式等投資運用に従事。2023年4月に既修者コースに入学、2024年在学中受験で合格。 |
|---|---|
| K.S. | さん:法学部出身。学部時代には司法試験受験歴なし。学部卒業後は民間企業の管理部門で勤務。2019年4月に未修者コースに入学、2022年3月に修了、3回目の試験で合格。 |
| T.M. | さん:経済学部出⾝。純粋未修者。約15年間、監査法人で金融機関の会計監査・コンサルティング業務に従事。その後独立し、直近7年間は個人会計士として活動。2021年4月に未修者コースに入学、2024年3⽉に修了、2回目の受験で合格。 |
| K.T. | さん:法学部出身。学部時代に旧司法試験、学部卒業後には旧司法試験・予備試験・新司法試験の受験歴(合計20回以上)あり。学部卒業後は民間企業数社の法務部門に在籍。2021年4月に既修者コースに入学、2023年3月に修了。2回目の試験で合格。 |
| O.T. | さん:法学部出身。学部時代には司法試験受験歴なし。(受験当時)公務員。2022年4月未修者コースに入学、2024年在学中に合格。2025年3月修了。 |
| 2 入学した経緯 | |
| K.K. | 私は、学部を卒業してから金融機関に勤務し司法試験とは全く縁のない生活を送ってきました。 もっとも金融機関における投融資においては法務、税務のリスクを評価してコントロールすることはとても大切で、弁護士、税理士等の専門家の方々と連携して仕事を進める機会が度々ありました。 その中で、弁護士、税理士をセカンドキャリアとして自然と意識するようになりました。2022年に税理士試験に最終合格したことから、本丸の司法試験への挑戦を決意して、働きながらでも通える筑波大学ロースクールに入学することとしました。 |
|---|---|
| K.S. | 私は大学在学中より、司法試験に合格して法曹として活躍することに憧れがあり、予備校で少し勉強したことがありますが、範囲の膨大さに挫けてしまい、卒業後は民間企業に就職しました。 社会人になって5年がたった頃、当時の夢が諦められず、仕事と両立できる筑波大学ロースクールを受験することを決意しました。 社会人になった後に行政書士の試験には合格していたのですが、既修者コースの入試を受験できるレベルの実力ではなかったのと、基礎的なところから法律を学び直したかったので、未修者コースに入学しました。 |
| T.M. | 私は、学部を卒業した後、公認会計士として監査法人に入所しました。 当初は銀行に対する会計監査業務とコンサルティング業務に従事していましたが、入所から10年ほど経ったときに東日本大震災があり、それをきっかけに東北の被災企業の復興支援業務にも関わるようになりました。その支援業務を通じ、中小企業の経営をサポートすることに使命とやりがいを感じ、独立して専ら中小企業を支援することにしました。 中小企業の社長達に日々伴走するなかで、彼ら彼女らの経営課題が多岐に及んでいるため税務・会計の知見だけでは限界があり、法的知識の必要性を感じることが増えてきました。 また、税理士登録の際に受講した講習で、「長崎年金二重課税事件」という著名な税務訴訟について教わり、世の中の常識とされていた実務をひっくり返して個人の権利を守れるという弁護士という役割に憧れを抱くようになりました。 そんな折にコロナ禍が始まって地方出張ができない状況に直面し、どうせ動けないなら腰を据えて法律を勉強して弁護士資格も実装しようと思い立ちました。諸々検討する中で、予備試験よりも確実性が高い法科大学院ルートが自分に合っていると考えました。 また、妻と二人の子供に加え、住宅ローンを抱えていた状況のため、仕事の継続は必須の状況でしたので、社会人に特化したカリキュラムをとっている筑波大学ロースクールであれば仕事と勉強が両立できるのではないかと考え、志望しました。 |
| K.T. | 私は、大学卒業後民間企業数社を転々としつつずっと法務部門で働いてきたのですが、2020年の秋頃に当時の所属会社の上司から「マネージャーにならないか」という話がありました。 チームには大手法律事務所出身の優秀な弁護士が数人いたことから、チームマネジメントの前に日本の法律に関する法的知識・分析能力を上げていかないと話にならないな、と思ったのが入学のきっかけです。 資格としてはすでに米国NY州の弁護士資格を取っていたので、司法試験合格というよりもそれに向けた勉強を重視していました。 |
| O.T. | 私は、大学入学前から法曹に憧れがあったのですが、大学時代の大半を部活動に費やしたため、そのままロースクールに進学することができませんでした。ただ、就職活動をしているときに、働きながら司法試験を受ける手段があって、社会人を対象とした筑波大学ロースクールの存在を知ることになり、将来的には筑波のロースクールに通うことを念頭において就職することを決意し、それに合った会社に就職することにしました。 そして、就職後、ある程度仕事を覚えて経済的に自立したタイミングを迎えたので、当初の計画通り筑波大学ロースクールを受験し、未修者コースに入学しました。 |
| 3 在学中の勉強方法、学業と仕事の両立方法 | |
| K.K. | 平日は朝7時過ぎに家を出て夕方の6時半くらいに帰宅する会社員生活の中で、とにかく学習時間の確保が課題でした。ロースクールの授業の難しさ・速さ、そして学生の皆さんの質の高さは相当なもので、それについて行かなければというプレッシャーもありましたし、授業内容は盛りだくさんで、2.5時間の授業の予習だけで5時間~10時間は必要でした。しかも予習のための作業を分割するとそれまでの思考、論理の積み重ねが一旦失われてしまい、リ・スタートするのに余計に時間がかかるため、平日も睡眠時間を削って時間を確保するようにしました。 工夫したのは、復習に使えるツール(ノートやカード、論証パターン)を作りながら予習したり授業を受けたりしたことです。授業の終了から期末試験までの期間が短いので、予習の段階で復習に使えるツールを作っておくことはとても時間と労力の節約になりました。 |
| O.T. | 私も、期末試験を念頭に置いて、そこでのポイントになりそうなところを中心に予習復習をすることに多くの時間を費やしました。私は、学校で良い成績を収めること=司法試験でも重要論点を抑えられる、という刷り込みを自分にして、とにかく勉強のほとんどを学校の試験・成績対策に使いました。 |
| T.M. | 私も期末試験に向けた予習復習を中心に勉強していました。特に私は非法学部卒の純粋未修者で、ゼロからの出発でしたので、講義を理解するために、出来る限り予習することを心掛けました。また、法律学習の場合はどうしても定義や基本概念などの定着が必要となりますので、まずは期末試験を当面の目標として復習し、知識の定着を図りました。 苦労したのは、期末試験では基本的に司法試験と同様事例問題が出題されますが、当初は起案の仕方が全く分からなかったことです。 この点、他の多くの学生の方はチューターゼミや自主ゼミなど、起案して第三者によるチェックを受ける機会を確保して補っていたものと思いますが、私の場合は顧問先から土日を問わず随時相談があり、決まった時間を確保することが難しかったことから、起案の仕方は答案例が記載されている予備校教材などを活用して独習しました。 |
| K.S. | 私は、今まさにT.M.さんがおっしゃったように、チューターゼミや自主ゼミを使って勉強を進めていました。 具体的には、1年次の時から積極的にチューターゼミに参加したり、同期と期末試験対策ゼミを組んだりしていました。 2年次以降は司法試験の対策を意識し、筑波の教授陣や修了生の先生方にお願いして、過去問を検討する自主ゼミを組んで頂いたりもしました。ゼミで学生同士答案を見せ合ったり、先生に添削をして頂いたりしたことによって、実践的な答案の書き方を早い段階から身に着けることができたと思います。 |
| K.T. | 私の勉強方法は復習中心で、期末試験前に定義や趣旨、構成要件を中心にノートを作りながら一気に復習するということを繰り返していました。新旧の司法試験をずっと受け続けてきたのでそのぐらいの勉強で足りたということかも知れませんが、本番の試験でも定義や要件を疎かにしていると全く点は付かなかったので、省エネの方向として間違っていたわけではないだろうと思います。 また、私も、在学中は途中から既修者コースの同期のゼミに入れてもらって、一緒に勉強しました。私が入学したときは、コロナ禍で授業は基本的にオンラインで、仕事との両立はしやすい環境だったと思いますが、情報共有の機会に乏しかったので、ゼミで仲間と集まることはそれだけで貴重な時間でした。 また、問題を解いた後に軽く議論するのがとても楽しかったですし、論文で書けても理解出来ていないことは口で説明できなかったりするので、議論を通じて自分が分かっていないところを確認するのに大変役立ちました。 |
| T.M. | 私も、K.T.さんと同じ2021年にロースクールに入学しており、コロナ禍で、ほとんどの授業はオンラインでした。これによって通学時間は節約できましたし、業務が自営業ということもあって、平日の日中が全て拘束されることはなかったため、業務が入っていない時間は全て勉強に充てることもできました。 また、3年次に在学中受験をしましたので、在学中受験要件充足と本試験の準備のため、2年次の夏からは顧問業務以外の案件は全て断り、より多くの勉強時間を確保しました。 要するに、私の場合、自営業ゆえに業務量を自身で調整して無理やり両立させたという感じなんですよね。フルタイム勤務であれば規定年数での修了が出来たかどうかも怪しく、少なくとも在学中受験要件の充足はほぼ不可能だったと思います。 |
| K.K. | 私が入学した2023年には、対面の授業も多くありましたが、オンライン参加も可能だったので、私も平日の授業は基本的にはオンライン参加で通学時間を節約しました。他方、土曜の授業はクラスの仲間と雑談できるよう登校して参加するようにしました。 通学時間で生ずる細切れの時間は、判例調査や定義暗記に充てるようにしました。 |
| K.S. | 私も、在学途中からコロナになって、授業のほとんどがオンラインになりました。 また、私の場合、当時の職場に、大学や大学院への通学を奨励する制度があって、上司や同僚にもロースクールに通うことを報告していましたので、通学中はなるべく残業にならないよう配慮いただき、恵まれた環境で勉強することができました。 とはいえ、予習をする時間はあまり取れなかったので、授業は復習中心で取り組みインプットを行い、ゼミでアウトプットの訓練をしていました。 |
| O.T. | 私は、業務時間内で仕事を終わらせることを第一に考え、就業時間中は細かく計画を立てながら全力で仕事をしていました。 そして、定時で上がった後のほとんど使える時間をフルで活用し、勉強時間に充てていました。 |
| 4 ロースクールの提供するもので良かったもの、足りなかったもの | |
| K.K. | 既修者コースの授業では、憲法が憲法Ⅲから、民法が民法Ⅶから始まるので、その前の内容については基本書で補う必要がありましたが、その他の科目のインプットはロースクールの授業・期末テストの内容だけで司法試験に十分合格できる質・量だと思います。特に、在学中受験を考えると、とても予備校のテキスト、問題集をフォローする時間はないと思います。 2024年の年明けから予備校の答練、模試を受けたのですが、それらの事前準備も基本的にはロースクールの授業を復習して臨みました。もちろん、授業で取り扱わなかった判例や論点も出てきますが、そういった未学習の論点に対しても、慌てることなく試験場で考えて食らいつく練習になりました。 また、選択科目は後回しになりがちなので、ペースメーカーとして月1回2年分の過去問を解く租税法のチューターゼミを受けたのですが、これはとても役に立ちました。過去問の起案を10年分以上添削していただいたので、選択科目の勉強はその復習だけで十分だったと思います。 |
| T.M. | 私も、筑波ロースクールには、比較的若い気鋭の先生が多く、教育にも熱心に取り組んでおり、法的知識ゼロの自分でも理解できるよう初歩から教えていただけたので、知識のインプットという面で非常に良かったと感じています。 このインプットという側面に関しては、全カリキュラムを通じて提供されたもので司法試験対策としても必要十分であったと感じています。 |
| K.T. | 私も、ロースクールの講義や教材等に不足があるとは思っていないです。 私は既修なので未修の方々が基礎科目において何を提供されているかは把握していないのですが、最初に手をつけた教科書や教材や過去問にずっと拘り続けると良いんじゃないかと思います。 特に社会人になってからは自分の自由になるお金が出来てしまうので(笑)、余計な本に目移りしがちです。読み物として楽しむならそれで良いのですが、受験対策としては絞り込んでそれを使い続けるのが良いだろうな、と。各科目、択一と論文の過去問に教科書が1冊あればそれで十分だと思っています。 あと、ロースクールで提供されたものの中で特に良かったものとして、科目によって先生の「まとめ」みたいな資料を提供頂くことがあったのですが、全体像を掴むのに非常に役立ちました。 試験に合格してある程度は基本書や資料を整理しましたが、このまとめ資料についてはきっと読み返すことがあるだろうと本棚に保管しています。 |
| K.S. | 私も、筑波ロースクールは、チューターゼミや自主ゼミなどで先生方の丁寧な指導を受けられる機会が豊富に用意されているところが素晴らしいと感じています。 他のロースクールでは、先生に答案添削やゼミをお願いし辛い環境であるところもあるらしいのですが、筑波では先生方が快く引き受けてくださり、大変ありがたかったです。 また、先生方も時間がない社会人学生ということを理解してくださっていて、コンパクトかつ無駄のない授業をしてくださっていると感じました。特に実務家教員の先生方の授業では、司法修習や実務に出てからも役立つような非常に実践的なお話を伺うことができたと思います。 施設については、自習室はコロナ期間を除いて、24時間使用できたのは大変ありがたかったです。 また、ゼミ室も数が多く、事前に予約すれば誰でも使えるのが便利でした。足りなかったものは、強いてあげれば、文房具や本などが購入できる売店等があればより良かったと思います。 |
| O.T. | 私も、チューターゼミ制度はかなり有意義だったと思います。ただ、2年次生のゼミでは、基本的に未修者と既修者が混ざって行われていますが、未修と既修では基礎知識量もゴールも違う(基本的に、未修は既卒1年目受験、既修は在学受験を目指す)ので、2年次生においても未修と既修でレベル分けをしても良いように思います。 また、私は利用する機会がなかったのですが、3年次生以降で利用できるゼミは各グループのニーズに応じた演習ができるので、こちらもかなり良いのではないかと思います。 |
| T.M. | あと、足りなかったものとして、強いて言えば「合格までのロードマップ」に対する伴走助言が挙げられるように思います。もちろん、社会人が前提の大学院ですし、ロースクールは受験指導をすべきでない、という建前は理解していますが、とはいえロースクールに入った動機はほぼ全員が司法試験の受験資格を得ることだと思いますし、最大の関心事は司法試験合格にあるという現実は否定できません。 この点については、授業でもある程度は先生方が教えてくれましたし、用意されているチューターゼミや自主ゼミなどで、ある程度科目ごとに補われている方もいらっしゃったと推察しますが、私のようにこれらの活用が難しい学生にとっては、基本的に自助努力に委ねられることとなります。 私の場合は、本試験までの残された時間に基づいてやるべきことを厳選し、そこから日々やるべきタスクを割り振って粛々と実行するという方法論を公認会計士受験時代に体得していましたので今回も実践できましたが、そうした経験がなければ相当厳しい戦いになったのではないかと思います。 このことから、自主ゼミやチューターゼミに参加できない学生のための工夫として、合格までのロードマップ作りや、その実現に向けた伴走支援のような仕組みがあると有難かったと感じています。 |
| 5 ロースクール修了から本試験まで | |
| K.S. | 私は3回目の受験で合格したのですが、1回目の受験では、短答を甘く見ていたため、足切りにあって短答不合格となりました。その後、2回目の試験に向けては、筑波の先生や同期の合格者のゼミに参加させて頂くとともに、外部のゼミにも参加し、過去問の起案を行っていました。 もっとも、論証集や短文事例問題集等をやりこんでおらず、過去問で見たことがない論点に対処できない、基本的な論証が即座に出てこない、という状態で2回目の試験本番を迎えてしまいました。 さらに、1回目の短答不合格の恐怖から直前期に短答対策に注力してしまい、論文をほぼ書かずに過ごしてしまったため、答案の型が崩れ途中答案を多く出してしまい、論文不合格となりました。 2回目の試験の結果を受けて、今までの勉強の全体的な振り返りと、2回目の試験について、設問ごとにどこができなかったのか、なぜできなかったのかを詳細に分析しました。 この分析を筑波の先生や合格者にも見てもらい、アドバイスを頂きました、さらに、年末に全科目の再現答案を作成し、これも筑波の先生や合格者に見て頂きました。 ここで敗因を徹底的に分析し、自分に必要な勉強を明確にできたことが自身の合格につながったと思います。敗因分析を受けて、短文事例問題集と論証集を周回することで基本的な知識を定着させ、論証の正確性と論点の網羅性を高めました。アウトプットに関しては、法的三段論法等、答案の型を死守することを特に重視して演習しました。緊張下の本番でも普段通りの自分で振舞えるよう、ゼミや答練、全国模試で意識的に演習していました。 筑波ローで基礎をしっかり学んでおりましたので、問題集や過去問の演習は比較的スムーズに取り組むことができ、筑波で学んでいてよかったと心から思います。 卒業して数年経つにもかかわらず、筑波の先生方は、添削や質問などにも快く対応してくださりました。 さらに、一緒に頑張る同期の存在も、勉強を継続する大きなモチベーションとなっていました。自分自身の力だけでは、到底合格はできなかったと思います。この場を借りて深く感謝申し上げます。 |
| T.M. | 私の場合、2024年3月にロースクールは修了しましたが、3年次では取得すべき単位も多くなかったことから、在学中受験の不合格結果が判明した11月初頭から、専ら本試験対策に注力しました。 具体的には、短答式過去問を40問(憲法10、民法20、刑法10)、論文式過去問のフル起案を一題こなすことを一日の学習量の最低ラインとして、時間がある日は他の問題集と定義趣旨等の暗記に努めました。 特に、在学中受験の反省として、短答式は8割程度とれたものの、大学院の期末試験以外に時間制限を設けて起案したことがほぼなかったことから、論文式では適切な時間配分もできず、全く歯が立たなかったということがありましたので、実際に時間を測って起案するという訓練を重視しました。 なお、在学中受験については、純粋未修者の私には振り返ってみると相当無理な挑戦であり、メリットもありましたが、結果としてはやめておいた方が良かったと感じています。 まず、メリットは、何といっても本試験を実際に体験でき、短答式さえ突破すれば論文の科目ごとの評価が得られるという点です。再現答案との比較対照で自分の弱点が客観視できますので、それを次年度に向けた学習の参考とできる点はメリットとして大きいと思います。 他方デメリットについては、第一に、貴重な受験回数を消費してしまう点です。私のように非法学部出身者の純粋未修者である社会人が在学中に合格する可能性は高いものではないというのが客観的な現実ですので、勝率の低い勝負に受験回数を消費してしまうのは得策とは言えません。 第二に、4か月の空白期間が生じることです。合格可能性が低いとは言うものの、受験した以上は「もしかすると合格しているのではないか」という希望が捨てきれず、試験がある7月中旬から発表がある11月上旬までの約4か月は、どうしても勉強の質・量が低下してしまいがちです。 いったん勉強が停滞すると、司法試験対応能力や勉強習慣を元に戻すためのリハビリから始めなければならず、実質的にマイナスからのスタートとなってしまいます。 これら二点のデメリットは、メリットを上回っているように思いますので、余程自信がない限りは修了後に満を持して受験することをお勧めします。 |
| K.T. | 正直なところ、私の過ごし方は全く他の方の参考にならないです。 というのも、ロースクール修了と同時に転職してそちらの方に意識が向いてしまい、1回目は週末にちょっと問題を解いただけで、2回目の受験は殆ど勉強に時間を使っていません。過去に予備試験に合格した直後に転職して同じような(受験面での)失敗をしたことがあるのですが、こうした移り気なところが私の悪いところです。受験するなら1回で合格すると決め、集中して臨むのが良いと思います。当たり前ですが・・・。 なお、本試験直前は、定義や趣旨を書いたロースクールの試験直前期のノートや講義で頂いたまとめ資料を読み返していました。 |
| O.T. | 私は在学中受験だったので、試験前の数ヶ月間も、当然授業・期末試験・レポートがありました。 ただ、教員の方々もそこは分かっているので、司法試験から大幅に外れるようなものを熱心に勉強させるようなことはない、、、と信じて、必修科目・選択科目問わず、愚直に授業で大事にされていた点をきっちり復習しました。ただ、それが影響してか、司法試験だけのための準備は直前1週間くらいしかなかったように思います。 |
| 6 これからのビジョンと後輩へのメッセージ | |
| K.K. | 私は、34年間の会社員生活に終止符を打ち、第78期司法修習に行くこととしました。 実際問題として、弁護士事務所入所後少なくとも数年は、収入が大幅にダウンすることになると思います。 しかし、年齢的にも新しいことを始めるには早い方が良いと考え、また、社会正義の実現に貢献できる弁護士の仕事にかけがえのない価値を感じたためです。 後輩の皆様へのメッセージとしては、まずは、仕事をしながらロースクールに通って司法試験を目指しておられる自分を褒めてください。すごいことです。ご家族を養っておられるならなおさらです。 そして折角同じ目標に向かって努力されているクラスメートがいるのですから、仲間になって励まし合って勉強を続けてください。資格試験の合格の秘訣は、合格するまで止めないことだと思います。 時には息抜きもして、目の前の課題に挑戦し続けることで、大きな結果を掴むことができると思います。ぜひ頑張ってください。 |
| K.S. | 私も、会社を退職し、第78期の司法修習に参加する予定です。 将来的には、これまでの経験を活かし、弁護士の資格を取得した上で、企業法務の分野で働きたいと考えています。 後輩へのメッセージですが、私自身ロースクールに入学する前は、法学の勉強が自分にあっているのかわからず、勉強についていけなかったらどうしようという心配があったのですが、筑波にはやる気がある学生をサポートする体制がしっかり整っていますので、入学を迷われている方はぜひ門戸を叩いてみてほしいと思います。 また、在学生の皆様におかれましては、1年次のうちから、司法試験の直前期に見返す資料を準備するというイメージで日々の勉強に取り組まれるとよいと思います。手を広げれば広げすぎるほど合格から遠ざかってしまうので、自分に必要なものをしっかり見極め、日々の学習を進めて頂くことが重要だと思います。 試験本番においては、最後はどれだけ自分を信じられるかの勝負です。 ぜひ、自分を信じて、合格に向けて全力で頑張って頂ければと思います。心から応援しています。 |
| T.M. | 私も、第78期の司法修習に行こうと思っています。 修習後は、現在経営顧問をしている顧問先にリーガルサービスも加えつつ、法律と数字の両者が分かるという弁護士×会計士としての強みを組み合わせ、コーポレートガバナンス・コードの担い手として上場企業の社外取締役への就任、新たな監査法人の設立を通じた資本市場への貢献、企業不正事案の第三者調査など、企業法務・会計分野で新たな挑戦をしていきたいと考えています。 これから司法試験に挑戦される皆様におかれては、とにかく奇をてらわずに、定義・趣旨の暗記、過去問演習といった地道な学習を繰り返すという王道を行き、合格を勝ち取って頂ければと思います。 昨今はSNSなどで情報が氾濫し、ともすると色々な勉強法や教材に目移りしがちですが、学習の対象とする教材を増やせば増やすほど合格は遠のくように思いますので、自分で選択した方法や教材を信じ、出来る限り繰り返して頂ければと思います。 皆様の合格と今後のより一層のご活躍を心より祈念しています。 |
| K.T. | 私は、ひとまずは現職での仕事を続けるつもりですが、いつか修習に行くかもしれません。 また、企業法務の道をずっと歩んできたので、この道で後進の育成に貢献すべく教鞭を取ることが出来たら良いなと考えています。 自分が真面目な受験生ではなかったので後輩へのメッセージというのは難しいですが、長い受験生活を経て一つ言えることがあるとすれば、この試験はよく言われるように実務家登用試験である、ということを意識すると良いと思います。 実務家になれば数多くの案件が舞い込んでくるのであり、それを淡々と高い品質で処理し続けていくには自分をどのように鍛えれば良いか。法務に触れたことがあるかどうかに関わらず、社会人の皆さんであれば既に自分なりの方法を見つけられているかと思います。 皆さんのご健闘、そしてその先に必ずある合格を、お祈りします。 |
| O.T. | 私は、第78期の司法修習に行く予定です。 これまで公務員として税に携わる仕事をしてきて、今回法律に関する資格を取れたので、修習後は、法曹として仕事をしつつ会計等の知識を増やし、会社が直面する問題に対して、税・法律・会計の各面から複合的に問題の解決策を考えられる人間となりたい、と考えています。 私は在学中、「仕事が忙しくて勉強ができなかった・成績が悪かった」ということは絶対に言わないようにしようと思っていました。 合格者の方のほとんどは、どんなに忙しくても勉強する時間を見つけて必死に授業に食らいつき司法試験合格に漕ぎ着けているのですから。仕事が原因だとしても、勉強する時間がないこと自体は単なる努力不足でしかないので、合格するためには、自分自身が必死になって勉強するしかないと言い聞かせてきました。 後輩やこれから入学なさる皆さまにも、是非そのように考えて、言い訳をしないで全力で取り組んで、合格を勝ち取ってほしいと思います。 |