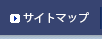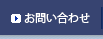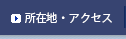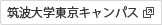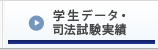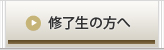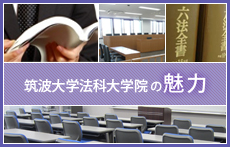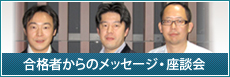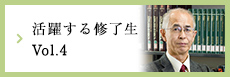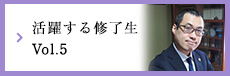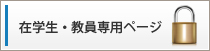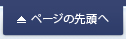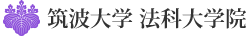株式会社大塚家具 大塚久美子社長へのインタビュー

| 株式会社 大塚家具代表取締役社長 大塚久美子さん 2014年3月法科大学院修了 |
|
|---|
|
大塚教授 |
本法科大学は開学して12年目を迎えまして“活躍する修了生”をテーマに連続で記事を計画しております。記念すべき第1回目として大塚久美子社長にお願い致しました。いま現在もご多忙な社長ですが、その当時も大変お忙しい中の学業だったかと思いますが、その点いかがでしょうか。 |
|---|---|
|
大塚社長 |
今回このようなインタビューの場を設定いただき、大変光栄です。その当時のことを思いだすと、授業に集中するのが難しかった時期もあったのを思い出します。 |
|
大塚教授 |
大変ご多忙な日々を過ごされていた訳ですが、すこし経歴を振り返らせていただきますと、社長は一橋大学の経済学部のご出身でいらっしゃいます。経済学を専攻するケインズ女子だったと聞いていますが(笑) |
|
大塚社長 |
はい、その通りです(笑)。元々経済が専門でしたので、法律を勉強するものとは思ってもいませんでした。最初はまったく肌に合いませんでした。法律の条文そのものがカタカナで書いてあってこれは日本語でないと思っていました(笑)。 |
|
大塚教授 |
その後、富士銀行に入行され、当時としては珍しい女性の総合職として勤務されていたとのことですね。 |
|
大塚社長 |
そうですね、富士銀行は当時女性の総合職を積極的に採用していました。融資担当でしたが、実際の現場は、経済だけではなく、法律の知識が意外と重視される世界でした。研修では金融法務等も勉強しました。 |
|
大塚教授 |
その後3年間勤務された後、大塚家具へ入社されたわけですね。 |
|
大塚社長 |
はい、当初、経営企画室に配属されました。経営企画室は、投資家向けのIR,広報その他企画全般を扱う部署でしたが、といっても経営の企画ばかりではなく、具体的な案件を扱うこともあり、トラブル解決のため海外へ飛んだこともあります。海外の法律事務所の弁護士と協同して解決にあたりましたね。 |
|
大塚教授 |
経営企画室ではかなり大変な案件も扱われたんでしょうか。 |
|
大塚社長 |
そうですね。企業の広報と具体的なトラブル解決とは意外に結びついています。会社のレピュテーションにも直接つながりますし。また、その中で感じたのは、弁護士さんを頼るにせよ、どれだけ説得力のある証拠を出せるかということについては、会社のことをよく知らないとどうにもならないということ。会社にある事実をよく知って、かつ法律家が重視するポイントを熟知しながら、それを探せるかに掛かってきます。結局会社と法律の両方を知らないとそれは探せないわけですよね。 |
|
大塚教授 |
いわば通訳的な役割ですね。 |
|
大塚社長 |
そうなんです。そういった通訳をする人が実際いないことがわかり、それはどこの企業でも困っているんだろうなと思いました。それが法律の勉強をするようになった動機です。また、経営企画として仕事をする際に、法律を意識することで、見える角度も違ってくると思いました。法律は社会の常識を洗練化したもの、基本とするものともいえると思います。それは会社において何かを規範化するときのガイドとして重要であることを知りました。 |
|
大塚教授 |
2005年に大塚家具を退社されてIRと広報を専門とするコンサルティング会社を立ち上げられ、翌2006年4月に本法科大学院へ入学されました。 |
|
大塚社長 |
 当時は小さな会社がIPOをする時代だったのでそういった会社の広報やIRを担うコンサル会社を立ち上げました。その当時は世の中で会社に対する規範の考え方が大きく変わるときでした。規範に対する考え方を誤ると企業のPRも誤ると感じていました。そうしたことで、危機管理や広報、もちろんコンプライアンス含めて、何を行うにも法律を理解することは必要であると思いました。 当時は小さな会社がIPOをする時代だったのでそういった会社の広報やIRを担うコンサル会社を立ち上げました。その当時は世の中で会社に対する規範の考え方が大きく変わるときでした。規範に対する考え方を誤ると企業のPRも誤ると感じていました。そうしたことで、危機管理や広報、もちろんコンプライアンス含めて、何を行うにも法律を理解することは必要であると思いました。 |
|
大塚教授 |
実際に筑波大学に入学してみていかがだったでしょうか。 |
|
大塚社長 |
入学して、まず、法律の専門家がこのように物事を考えるんだということで、大きなカルチャーショックを受けました。たとえば、経済学では生の事実からどう理論を作っていくかを考えるのですが、法律学では、最初に決まった理屈があって、それを生の現実に当てはめようとする。まったく逆のアプローチに感じました。はじめは本当に違和感がありました。法律の枠があって、その枠にはめられたという感じが、最初大きくありました。その後になってですが、解釈論で現実の妥当性を図っていくことを知っていくのですが、とにかく最初は息苦しさがありましたね。 |
|
大塚教授 |
実際に通われてみて、徐々に法律には慣れましたでしょうか。 |
|
大塚社長 |
徐々になれました。とくに答案の書き方を理解するまで難しかったですが、徐々に自分で理解することができるようになりました。ものの考え方として、法律が想定する原則と例外等が区別できるようになって、そうですね、2年過ぎた頃ですね、慣れた感じがしました。 |
|
大塚教授 |
在学中の勉強で既に役立ったことはあったのでしょうか。確か在学3年目には大塚家具に戻られたようですが。 |
|
大塚社長 |
大塚家具に戻ってから忙しくなりしばらく休学していました。大学での勉強は、物事の理解の仕方で大変役に立ちました。また、自社の顧問弁護士の先生と会議をするのですが、はるかに効率的になりました(笑)。社内で社員に話すときも、こういったことを中心に整理して弁護士さんに相談すればいいのでは等言えるようになりました。 |
|
大塚教授 |
漠然とした質問ですが、会社の法務部の在り方についてどうお考えでしょうか。 |
|
大塚社長 |
先程話がありましたが、「通訳」できることが重要だと思います。もちろん多くの案件は弁護士の先生に相談せずとも、法的なことに対処できることが一義的には重要です。しかし、法務部だけでは判断できないような案件については、弁護士と会社との間の通訳として、会社と法律に精通していることが重要だと思います。特に会社のコンプライアンスについていえば、たいていの会社内部の問題は、故意ではなく、気が付かずに起きているので、細かく目配りをすることが大切ですね。また法の趣旨を理解することが大切だと思いますね。たとえばガバナンスコードを見ると、企業価値をあげるためのものであると目的を明確にいっているわけでして、それをきちんと理解していくことです。経済をよくするためのコーポレート・ガバナンスであるとすれば、その趣旨が実行できるようにガバナンスを作ることが大切だと思います。細かい規則だけに気を取られ形式的に構築することを考えると息苦しくなるでしょうね。 |
|
大塚教授 |
リスクを伴った案件で、法務部の果たす役割について、難しい問題かもしれませんが、いかがお考えでしょう。 |
|
大塚社長 |
リスクを伴った案件について、リスク管理の観点から別の目をいれることは重要ですが、法務担当がすべてこれを担保して対応できるとは思っていません。リスクを少なくすればそこで仕事が終わりと考えがちですね。弁護士さんもとにかくリスクを小さくするというアドバイスだけになりがちです。でもそれだけだとビジネスは成り立たないわけです。それがどの程度の法的なリスクなのかを理解した上で、チェックをする側としても、どこまでが法務の立場でNOというべき問題なのか、どこからが経営判断の問題なのかを考えないといけないでしょう。その切り分けを誤るとまずいことになると思いますね。難しい判断でありますが。 |
|
大塚教授 |
法務部も経営的な思考をもって、「通訳」をしてくれないといけないわけですね。 |
|
大塚社長 |
リスクをどの程度許容できるかは、まさに経営判断なのでしょう。リスク・ゼロは利益ゼロであって、経営は成り立たないわけですからね。法務部を通すことは重要ですが、最終は経営判断だということです。難しさは実感していますが、、、。 |
|
大塚教授 |
現在本法科大学院に在籍している学生、彼らはすべて社会人ですが、どういう学び方をすべきであるか、メッセージをいただけないでしょうか。 |
|
大塚社長 |
常に現実の問題と結びつけて考えることでしょうか。授業の中には、実際直面している事例と類似のケースが授業で取り上げられる場合もあり、それが結構リアルであって、教室で座学として勉強しているとそうでもないが、授業を離れて社会人としてみるとリアルさがわかってきます。授業では直接経験しないようなケースも勉強するのですが、なるべくリアルな状況を想起できるようにするとそれが役に立つ知識になると思います。私自身はビジネスの世界の人間としてそう思いますが、法曹になられる方も、企業側の立場を理解しつつ法律の論理をもつという「複眼的な視点」を持つことが必要なのではないのでしょうか。 |
|
大塚教授 |
法律家としての想像力をもつということでしょうか。 |
|
大塚社長 |
話をしていて、どんなに小さな案件でも、こういう問題になる可能性のある話だよねとか、積み重なると大問題に繋がる可能性があるね、というと急に顔色が変わるわけです。普段は問題性を感じていないわけで、そういった想像力をもつことが大切で、法律を勉強することでそういった想像力が働くようになると思いますね。 |
|
大塚教授 |
たしかに何かあったときに、想像力をもった法律家になることは重要ですね。 |
|
大塚社長 |
複眼的な視点ということですが、相談できる社内の法務部という観点では、どうやったら適法にきちんとそれができるのか、という観点で相談に応じてくれれば有難いのですが、それはできませんというだけで、だったらどうすればいいというところまでは、なかなか行かないのではないでしょうか。そうではなくて、こうすれば同じ結果が得られるのではないですか、という提案ができる法務が理想でしょうね。 |
|
大塚教授 |
経営トップであられる大塚社長へ伺いたいのですが、法科大学院の学生にこういう力を身につけてほしいといった要望はありますか。 |
|
大塚社長 |
 ビジネスの視点をもった法律家をいつも経営者は求めています、同じ目線で自分とは違う専門的な知識をもってアドバイスできる方ですね。法科大学院は様々な企業で働いている学生の方がいらっしゃるので、同じ目線で相談できる専門家になっていただきたいです。法律と経済の両方の知識を持っている法律家がいらっしゃれば、その方はとても企業から重宝されるのではないでしょうか。最近はいろいろな分野で2つの知識がある人材が重宝がられています。経営と技術の分野もそうですよね。これら両方の知識がある、いわばバイリンガルが求められていると実感しています。 ビジネスの視点をもった法律家をいつも経営者は求めています、同じ目線で自分とは違う専門的な知識をもってアドバイスできる方ですね。法科大学院は様々な企業で働いている学生の方がいらっしゃるので、同じ目線で相談できる専門家になっていただきたいです。法律と経済の両方の知識を持っている法律家がいらっしゃれば、その方はとても企業から重宝されるのではないでしょうか。最近はいろいろな分野で2つの知識がある人材が重宝がられています。経営と技術の分野もそうですよね。これら両方の知識がある、いわばバイリンガルが求められていると実感しています。 |
|
大塚教授 |
このような考え方を持っている大塚社長は、とても国際的な感覚を持っていらっしゃるように思いました。 |
|
大塚社長 |
知的財産権の分野ではかなり国際的な動きがあります。家具のデザインに著作性を認める潮流があって、ビジネスの枠組みが変わるような動きがあります。特にヨーロッパではそういった方向が顕著のようですね。デザインと美術の境目ですとか、デザイナーとアーティストの作品の保護をどうするか、といった問題意識に現れます。私共の分野でも、そういった意味で海外の動向は目が離せない状況ですね。 |
|
大塚教授 |
大塚社長から見て、今後法科大学院はどのようになると思いますか。 |
|
大塚社長 |
もう少し広い素養を持った法曹人を育成するか、或いはいま現在の法曹養成の体制を維持するかによって変わると思いますが、大学側の意識としては後者にあるのかなと思います。ただ、法律を学ぶ側にとってみれば、多くの時間とお金がかるのですが、他方で法曹実務家のための法律教育は3年もあれば効率よく学べるだろうと思います。学生は、学ぶ側として法科大学院をどう使うかの選択肢があるので、それを考慮して勉強に取り組んでほしいですね。 |
|
大塚教授 |
社長は時間をかけて修了されましたが、仕事との二足のわらじで大変な中、とても努力されたのではないでしょうか。 |
|
大塚社長 |
8年目で最後の単位数を取得した際、あきらめずに勉強を頑張ってよかったと思いました。途中くじけそうになった時もありましたが、7年勉強して修了せずにあきらめるより、8年かかってもいいから修了したいという気持ちで頑張りましたね。 |
|
大塚教授 |
法科大学院での学びで、リターンはありましたか(笑)。 |
|
大塚社長 |
学んだことのリターンはありました。経済的なものかは別にして、学んだことは自分の中に確実に残るものです。人生には予想外の出来事が多くありましたが、結果的に大学院での学びは役に立つものだと思います。最後まで授業に出て試験も受けると、それなりにきちんと勉強することになります。試験がないと勉強しませんしね(笑)。役に立てるかどうかは、やはり自分次第なのではないでしょうか。 |
|
大塚教授 |
これからも社長のますますのご活躍をお祈りしています。 本日はお忙しい中ありがとうございました。 |